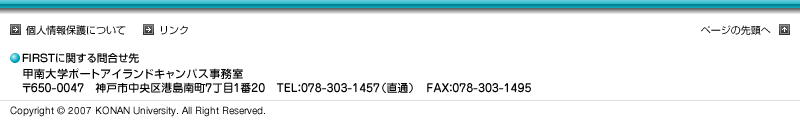| 科目名 | 生物有機化学 |
|---|---|
| 配当年次 | 2年次(B期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 月曜2限、金曜1限 |
| 担当教員 | 甲元 一也 |
| 講義方法 | プリントを配布し、それに沿って授業をすすめる。 |
| 概要 | 生体内の化学反応の多くは、20種類のアミノ酸を重合して作られた蛋白質(酵素)によって触媒され起こる。酵素の類い希なる分子認識能と触媒活性、特に、有機反応が不利な水中においてすら効率的に進むその反応性は、特徴的な立体構造と側鎖の官能基がもたらしている。本講義では、酵素が起こす種々の化学反応を、有機化学の視点から眺め、触媒反応が起こるメカニズムを学習する。また、核酸、蛋白質、糖鎖の人工合成を例に出し、天然系と合成系の違いや人工系ならではの工夫を学習する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 本講義では、生物と化学の融合分野を化学の視点から眺め、化学、生物の講義で独立に学んだ知識を融合し、総合的に理解・活用できるようになることを目指す。 ・酵素反応を有機化学的な視点から考えることができる ・生体分子の構造と機能を理解する ・人工的に生体分子を合成するための有機化学の工夫を知る |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 試験(80%)、レポート(20%)から評価する。 |
| 講義構成 |
1.生体を構成する分子とその機能 2.アミノ酸、ペプチドとタンパク質の化学 3.タンパク質の高次構造 4.溶媒の役割 5.有機化学と溶媒 6.触媒反応と遷移状態の安定化 7.相互作用とタンパク質の構造と機能 8.構造安定性や酸化還元反応に関わる金属イオンや補酵素 9.酵素触媒機構1 10.酵素触媒機構2 11.生体高分子の化学合成(1) −液相合成と固相合成− 12.生体高分子の化学合成(2) −逐次合成法と保護、脱保護− 13.生体高分子の化学合成(3) −縮合剤と活性エステル− 14.ペプチドの化学合成 15.核酸の化学合成 |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | 「ジョーンズ有機化学(上、下)第3版」(東京化学同人) 「ライフサイエンス有機化学」、飯田隆著、共立出版 「入門 酵素と補酵素の化学」(T.D.H.Bugg著、井上國世訳、Springer出版) 「酵素反応機構」、E.ゼフレン・P.L.ホール著、学会出版センター 「分子認識と生体機能」、小宮山真・荒木孝二著、朝倉書店 |
| 備考 |
|