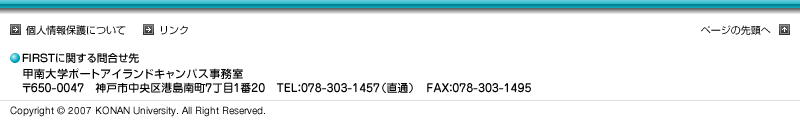| 科目名 | 有機反応各論 |
|---|---|
| 配当年次 | 1年次(D期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 火曜1限、木曜2限 |
| 担当教員 | 松井 淳 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 有機化学を学ぶ究極の目的は、望みの物質をできるだけ効率よく合成する手段を見出す、あるいは開発する能力を身につけることである。本講義では、そのような能力の習得に欠かせない各種有機化合物の反応性を学ぶことを目的として、さまざまな有機反応を系統的に列挙しながら、その反応機構を解説し、各種有機化合物の物性や反応性を決定づける官能基の構造と性質について網羅的に解説する。さらに、実際によく使われる有機反応を例説しながら、身につけた知識を組み合わせて、医薬品や新素材などの役に立つ有機化合物の合成に活かす能力の基礎を養う。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 求核付加反応、求核置換反応、脱離反応などに関する機構を理解し、生成物の推定や、生成物から反応経路を考案できるようになることを目標とする。 この授業では、化学反応に関する知識を整理し、それえらの知識を目的に応じて引き出し、組み合わせられるようにトレーニングする過程で、次の[社会で役立つ能力」が習得できます。 ④論理的に思考する力 ⑤情報を整理し分析する力 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 期末試験を中心に評価を行う。 |
| 講義構成 |
1.講義の進め方、化学反応の基礎 2.求核置換反応、ハロゲンを持つ化合物 3.酸と塩基(1) 脱離基 4.Grignard試薬の反応 5.アルコールの性質と反応 6.エーテルの性質と反応 7.アミンの性質と反応 8.脱離反応 9.アルデヒド、ケトンの性質と反応 10.カルボン酸およびその誘導体の性質と反応 11.酸と塩基(2) 12.ケト‐エノール互変異性 13.アルドール反応、Claisen反応 14.炭素‐炭素結合を生成する反応 15.アルコール、カルボン酸誘導体の合成法 |
| 教科書 | ジョーンズ有機化学(上、下)第3版(東京化学同人) |
| 参考書・資料 | |
| 備考 |
|