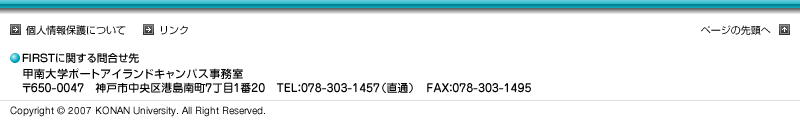| 科目名 | 構造有機化学 |
|---|---|
| 配当年次 | 1年次(A期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 月曜1限、金曜2限 |
| 担当教員 | 甲元 一也 |
| 講義方法 | 配付資料(プリント)に沿って、講義をすすめる。 |
| 概要 | 有機化合物は、原子間の電子の共有(共有結合)によって形成され、その構造は各原子における混成軌道の組み合わせによって決定される。本講義では、分子における電子配置と分子軌道の基礎的概念を理解し、化学構造式から有機化合物の立体構造を洞察できる思考を身につける。また、立体構造によって生じる不斉炭素や構造異性体について学習する。さらに、有機化合物に対する一般的な名称の付け方についても学習する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 有機化合物の立体構造を理解し、イメージできる理論と“眼”を身につける。 ・電子と共有結合について理解する ・化学構造式から分子の立体構造をイメージできる ・立体化学と不斉について理解する ・一般的な有機化合物の名称がわかる |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 試験(80%)、レポート(20%)から評価する。 |
| 講義構成 |
1.科学における有機化学の役割 2.原子と分子(1 −軌道と共有結合− 3.原子と分子(2) −Lewis電子式とオクテット則− 4.原子と分子(3) −共鳴構造式− 5.アルカン、アルケン、アルキン −混成軌道− 6.アルカン −コンフォメーション異性体とNewman投影式− 7.有機化合物の命名法(1) −アルカンの命名− 8.アルケン、アルキン −π結合と幾何異性体− 9.有機化合物の命名法(2) −異性体の命名− 10.立体化学(1) −光学異性体とR/S表示法− 11.立体化学(2) −エナンチオマーとジアステレオマー− 12.環状化合物(1) −環状化合物の構造− 13.環状化合物(2) −安定コンフォメーション− 14.共鳴と反応性(1) −立体化学と共鳴・共役− 15.共鳴と反応性(2) −電子の偏りと酸塩基の強さ− |
| 教科書 | ジョーンズ有機化学(上)第3版(東京化学同人) |
| 参考書・資料 | ライフサイエンス有機化学(立体化学・生体分子・物質代謝)共立出版 |
| 備考 | 高等学校の化学を履修していない学生にもわかるよう、基礎的な部分から授業を開始し、補足資料やレポートによって理解を深められるよう工夫しながら授業を進めます。 |
|