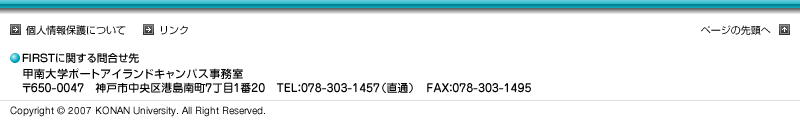| 科目名 | ナノテクノロジー |
|---|---|
| 配当年次 | 2年次(B期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 火曜2限、木曜2限 |
| 担当教員 | 赤松 謙祐 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 物質のサイズがナノスケールになると体積に対して表面の占める割合が著しく増加し、さらに電子構造も変化するため通常では見られない特異な物性が発現する。近年の材料技術の発展において、先端材料と呼ばれる材料のサイズはナノメートルサイズに近づきつつあり、このナノサイズ物質が示す性質を利用した先進技術「ナノテクノロジー」は21世紀を支える根幹技術となりえる。今後ナノテクノロジーを様々な既存技術と融合、発展させる場合に、ナノサイズ領域で発現する様々な現象の本質的理解は重要である。本講義では、このサイズ領域で発現する種々の現象や起源および応用例について概説する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 目的:物質のサイズ効果について理解し、テクノロジーと材料スケールの関係についての素養を身につける。 理解・達成目標: 1.固体構造と電気・光物性について理解する 2.金属・半導体・磁性体のサイズ効果がわかる 3.微細加工技術を微細構造観察技術についての基礎を身につける |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 出席、レポート提出および期末試験により総合的に評価する。 |
| 講義構成 |
1.序論「ナノテクノロジー」とは 2.原子・分子・バルク材料の構造 3.ナノサイズ物質の電子構造「金属・半導体・絶縁体・磁性体」 4.表面効果1「融点降下、易焼結性とその応用」 5.表面効果2「触媒活性の増大とその応用」 6.サイズ効果1「金属ナノ粒子の表面プラズモン共鳴」 7.サイズ効果2「半導体ナノ粒子の発光」 8.サイズ効果3「磁性ナノ粒子の性質」 9.ナノ材料を用いたバイオセンサー 10.微細加工技術「リソグラフ・2次元、3次元造形」 11.微細構造観察技術「電子顕微鏡、原子間力顕微鏡」 12.光・電子材料への応用「光ディスク・導波路・単電子トランジスタ」 13.記録材料への応用「テラビット磁気メモリ」 14.エネルギー変換材料への応用 15.ナノテクノロジーの実用化への課題と将来展望 |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | 「ナノテクノロジーの基礎科学」M. Wilson他 著、小薗井薫 訳、NTS出版 「図解 ナノテクノロジーのすべて」、川合知二監修、工業調査会 |
| 備考 |
|