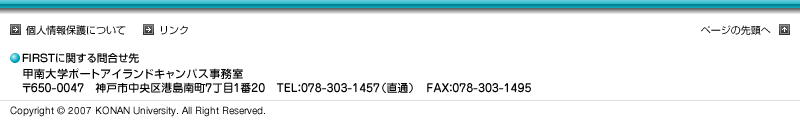| 科目名 | 薬理学 |
|---|---|
| 配当年次 | 2年次(D期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 月曜2限、木曜2限 |
| 担当教員 | 川上 純司 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 薬とは何か?というところから出発し、医薬品がどのように働くのかを、生命分子との相互作用を中心に解説する。代表的な医薬品に関して標的分子と薬剤の基本骨格を学び、官能基レベルでの相互作用が薬効と副作用にどのような影響を及ぼすかを理解する。更に、病気の発症メカニズムを知ることで、どのような生命分子を標的とした薬剤が医薬品になりうるかを考察する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 相互作用を基本とした薬剤の作用メカニズムを通して、創薬研究のためにどのような知識と考え方が必要であるかを理解する。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 講義中の質疑応答、出席状況、小テスト、レポート、期末試験の結果を総合的に判断する。 |
| 講義構成 |
1.序論:薬とは何か? 2.医薬品の作用機序:分子間相互作用と薬理活性 3.薬理活性の発現1:結合定数, 薬効と副作用(高親和性と特異性) 4.薬理活性の発現2:吸収、分布、消失 5.薬理活性の発現3:アゴニストとアンタゴニスト 6.交感神経と副交感神経:神経伝達物質の構造的分類 7.神経系作用薬1 8.神経系作用薬2 9.オピオイド 10.解熱・鎮痛薬 11.抗炎症薬 12.循環器系作用薬 13.泌尿器系作用薬 14.抗菌薬・抗ウイルス薬・抗がん剤 15.新規医薬品開発:標的分子、 医薬品の基本骨格とパーツ |
| 教科書 | 「くすりの地図帳」伊賀立二・小瀧一・沢田康文/監修(講談社) 「イラスト生理学 改訂第2版」照井直人/編(羊土社) |
| 参考書・資料 | |
| 備考 |
|