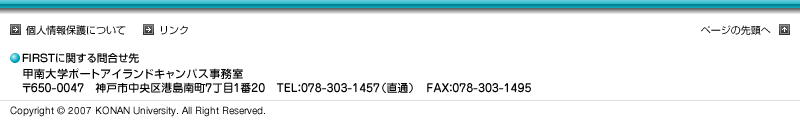| 科目名 | メディカルサイエンス概論 |
|---|---|
| 配当年次 | 2年次(A期+集中講義) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 水曜1限(2年次 A期)、集中講義 |
| 担当教員 | 藤井 敏司、三宅 正人 |
| 講義方法 | パワーポイントを用いた講義。理解を深めるための意見交換、講義内容を確認するためのテストを含む。 |
| 概要 |
(藤井) 生体内に存在する分子の働きや、分子間の関わり合い(ネットワーク)に関する情報は、ひとの健康や医療を考える上で欠かせないものである。本講義では血圧調整・記憶形成などにおけるシグナル伝達物質として知られる一酸化窒素(NO)と、遺伝情報や細胞内の性質を支配する核酸(DNAなど)やタンパク質に注目しこれら物質の化学的・生理学的側面から、研究の最前線(生体内分子イメージング、DNAチップ、プロテインチップなど)、さらには創薬・医療への応用までを幅広く解説し、科学から医療や健康を捉える視点を養う。 (三宅) 健康・医療産業には数多くの細胞生物学やゲノム科学の知識が応用されています。その結果、細胞を用いた再生医療や個人の体質に合わせた個別化医療等の未来の医療の姿も見えてきています。本講義では、創薬や診断、その他の産業に応用されているゲノム解析技術、細胞解析技術について最近の新聞記事等に取り上げられた事例なども含め概説する予定です。本講義を通して、これからの医療や健康産業の在り方、技術開発の方向性等を考えるための視点を養うことを目指します。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | (藤井) ・医療・健康産業に関係する基礎科学を理解し、応用出来る基盤技術の基礎を身につけること。 ・活性酸素、一酸化窒素の生理作用について理解すること。 ・核酸、タンパク質の関係する疾患について基礎を理解すること。 (三宅) ・創薬や診断技術を理解するために必要な専門用語が説明できるようになること。 ・創薬や診断技術に応用されている生物化学的原理が説明できるようになること。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | (藤井) レポート及び講義内で行う確認テストによって評価する。 (三宅) 講義内で行う確認テストによって評価する。 最終成績は藤井分(50%)、三宅分(50%)を総合して評価する。 |
| 講義構成 |
(藤井) 1.医学を科学として考える 2.活性酸素について:活性酸素とは。活性酸素と疾患。活性酸素と健康 3.一酸化窒素について(1):一酸化窒素の生理作用 4.一酸化窒素について(2):一酸化窒素の関与する疾患 5.核酸と疾患:活性酸素の関与 6.タンパク質と疾患:活性酸素との相互作用。コンフォメーション病 7.生体内分子イメージング:蛍光、磁気共鳴、PET 8.チップ化技術 (三宅) 2日間の(午前・午後)の集中講義。 1日目:ゲノム解析技術と創薬、診断、産業応用。(ゲノム配列解析、ジェノタイピング、発現解析等) 確認試験 2日目:細胞解析技術と創薬、診断、産業応用。(一細胞解析、システム生物学的アプローチ等) 確認試験 |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | |
| 備考 | A期と集中講義に分かれているが、併せて一つの講義科目なので、履修する人は注意してください。どちらか一方だけ履修した場合は、欠席扱いになります。 医学を科学としてとらえてみましょう。我々の学部は医学部ではないので、実際に患者さんに対する医療行為はできませんが、基礎医学的な部分、医用工学的な部分では医療に貢献することが可能です。これらの分野の基礎的な部分を学んでみましょう。 |
|