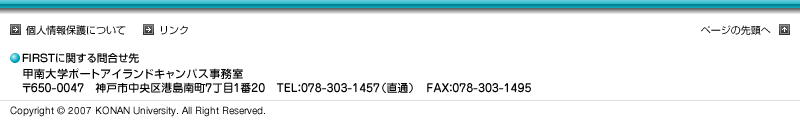| 科目名 | 創薬テクノロジー |
|---|---|
| 配当年次 | 3年次(B期+集中講義) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 木曜2限(B期)+集中講義 |
| 担当教員 | 川上 純司、二木 史朗 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 近年の分子細胞生物学や構造生物学、ゲノム生物学の目覚ましい発展により、病変と関連した細胞機能の分子レベルでの理解とこれに基づく新しい創薬が進められてきた。本講義では、いくつかの新薬の開発例を元に、(i)どのような生体内分子が創薬ターゲットとして注目されているか、(ii)薬物によりこれらの分子の機能をどのように調節することが治療につながるか、(iii)これらを可能とする薬物はどのように発見あるいは設計されたかを解説し、21世紀の創薬における戦略とテクノロジーを概観する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 創薬研究をイメージではなく具体的に理解する。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 講義中の質疑応答、出席状況、小テスト、レポート、期末試験の結果を総合的に判断する。 |
| 講義構成 |
(川上) 1.序論「創薬」とは 2.医薬品の開発プロセス:シード化合物の探索から医薬品としての認可まで 3.薬理活性物質と医薬品:製剤とDDS 4.分子標的医薬とライブラリースクリーニング 5.経験則の蓄積と薬剤設計:薬剤の基本骨格とファーマコフォア 6.薬剤設計の実際:生物学的等価性 7.薬剤設計の実際:Hansch-Fujitaの式、Craigプロット、Toplissツリー 8.ゲノム創薬とテーラーメード医薬品 (二木:集中講義) 第1回 従来の医薬品の多くは、生理活性を持つ天然物などから薬効成分をスクリーニングすることによって得られてきたが、近年、病態に関わる生体内の特定の分子を狙い撃つような薬物(分子標的薬)が使われるようになってきた。ここでは、抗がん薬として使われる分子標的薬(小分子・抗体医薬品)を取り上げ、その設計や薬効に関して紹介する。 第2回 ウイルスは、宿主細胞に感染し、その細胞機能を利用して増殖するため、細胞内でのウイルスの増殖を選択的に抑制する薬物の開発は一般に容易ではない。しかし、ウイルスの増殖機序が明らかになるにつれ、様々な薬物が開発されるようになってきた。ここでは、インフルエンザやヒト免疫不全ウイルス(HIV)を例に、これらの治療薬の開発の試みを紹介する。 |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | 適宜、資料を配付する。 |
| 備考 |
|