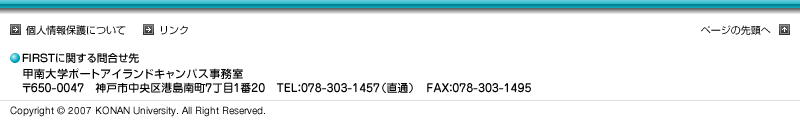| 科目名 | ケミカルバイオロジー |
|---|---|
| 配当年次 | 3年次(B期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 水曜2限、金曜2限 |
| 担当教員 | 三好 大輔 |
| 講義方法 | スライドと板書を組み合わせて説明する。 |
| 概要 | ケミカルバイオロジーは化学(ケミストリー)と生命科学(バイオロジカルサイエンス)の融合によって生み出された新しい研究領域である。バイオインフォマティクスやシステムバイオロジーなどと並んでポストゲノム時代である21世紀の生命科学の基盤となる可能性を有している。また、ケミカルバイオロジーは多様な有機化合物を駆使して生命に関する研究を進めることから、医薬品などに直結する有用な化合物開発にも必要な研究領域でもある。実際に、米国ではNIH(国立衛生研究所)の将来戦略5本柱の1つとして推進され、様々なケミカルゲノミスプロジェクトが2004年より開始されている。また、日本においても日本ケミカルバイオロジー学会が設立されるなど、国内外で注目を集める研究・学問領域である。本講義では、このように広範な研究・産業分野において注目されるケミカルバイオロジーを理解する上で必要な基礎知識、要素技術、関連研究分野を系統的に解説する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 化学で生命現象を解析するために必要な知識と考え方を習得する。また、関連研究分野について、積極的に調査できる素養を身につける。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 出席、レポート、期末試験を総合して評価する。また、講義内容に関する理解度を確認する小テストを行う場合がある。 |
| 講義構成 |
1.序論:ケミカルバイオロジーとは 2.生体分子の情報と構造 3.生体分子の機能と相互作用 4.生体分子とリガンド 5.核酸医薬 6.コンビナトリアルケミストリーとケミカルライブラリー 7.生体分子の化学的修飾方法 8.バイオプローブとバイオイメージング 9.エピジェネティクスとケミカルバイオロジー 10.創薬とケミカルバイオロジー 11.ケミカルバイオロジーの実際 12.まとめ |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | なし |
| 備考 |
|